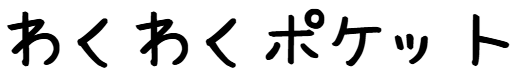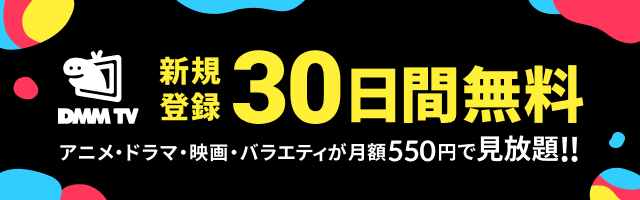明日の天気はどうなるかな?
自然の様子を観察することで、天気の変化を予測する方法があるのを知っていますか?
これは「観天望気(かんてんぼうき)」と呼ばれ、昔から人々に親しまれてきました。
ここでは、誰でもわかりやすいように、身近な観察ポイントを紹介します。
さぁ、みんなも天気予報をしてみましょう!
雲の観察で天気を予測しよう
空に浮かぶ雲の形や動きから、天気の変化を読み取ることができます。
積乱雲(せきらんうん)
もくもくと大きく発達した雲
雷雨やにわか雨をもたらすことがあります。
巻雲(けんうん)
薄くてすじ状の雲
空一面に広がると、天気が下り坂になる前触れかもしれません。
飛行機雲で分かること
飛行機雲は、ある程度の天気予報の参考になります。
飛行機雲は、飛行機の排気ガスに含まれる水蒸気が上空の冷たい空気で凝結してできる雲です。その形や持続時間から、大気の状態を推測できます。
飛行機雲 がすぐ消える時
飛行機が通過したあと、すぐに雲が消える場合は晴天が続くと予想できます。
• 上空の湿度が低く、乾燥している状態。
• 高気圧に覆われているため、天気は安定しやすい。
長く残る飛行機雲(太く広がる)
飛行機雲が長い時間残っている場合は、雨が降る可能性が高くなっています。
• 上空の湿度が高く、雲ができやすい状態。
• 低気圧や前線が近づいている可能性があり、雨が降るかもしれない。
鳥の行動で天気を予測しよう
昔から「ツバメが低く飛ぶと雨が降る」といわれています。もちろん、科学的な天気予報には及びませんが、自然の観察を通じて天候を予測する一つの方法として使えます。
鳥が高く飛んでいるとき
晴れの日が多いです。
気圧が高く、上昇気流が発生しやすい晴れの日には、鳥は高く飛びやすくなります。
鳥が低く飛んでいるとき
雨が近いかもしれません。
湿度が高くなると、昆虫が低く飛ぶため、それを餌にする鳥も低空を飛ぶ傾向があります。
群れをなして飛ぶ鳥
嵐や悪天候が迫っている可能性があります。
鳥は気圧の変化を敏感に感じ取るため、安全な場所に移動することがあります。
飛ぶのをやめてじっとしている鳥
嵐や強風が近いかもしれません。
鳥は強風を避けるために飛ぶのを控え、安全な場所にとどまることがよくあります。
動物の動きで天気を予測しよう
動物たちの動きにも、天気のヒントが隠されています。
アリが巣の入り口をふさぐとき
雨が近いとされています。
アリは気圧の変化を敏感に感じ取り、雨が降る前に巣の入り口をふさぐことがある。
トンボが低く飛ぶとき
雨が降る前兆とされています。
気圧が低いと飛ぶのに余計なエネルギーが必要になり、トンボが低く飛ぶ傾向があると言われています。
また餌となる小さな虫も、雨が近づくと湿度が上がり、空気中の水分が増えて昆虫の羽が重くなるため、低く飛ぶようになります。その為それを狙うトンボも自然と低く飛ぶようになるとされています。
カエルがよく鳴くとき
雨が近いサインとされています。
湿度が高くなるとカエルは活発になり、鳴き声が増えるため。
猫が顔を洗うとき
雨が降る可能性が高くなります。
湿気が増えると、猫のヒゲが敏感に反応し、顔をこすることが多くなると言われる。
植物の様子で天気を予測しよう
植物の変化も、天気の予測に役立ちます。
タンポポの綿毛が飛ばないとき
湿度が高く、雨が近い可能性があります。
松ぼっくりが閉じるとき
湿度が高く、雨が降る前兆とされています。
夕焼けや朝焼けで天気を予測しよう
空の色合いからも、天気の変化を読み取ることができます。
夕焼けが赤いとき
「夕焼け晴天」と言われるように、西の空が赤く染まると翌日は天気が良くなることが多い。
朝焼けが赤いとき
「朝焼け雨」と言われ、朝に空が赤くなると天気が崩れることが多い。
風や気温による予測方法
急に冷たい風が吹く
低気圧が接近している可能性が高く、雨が降る可能性が高いです
朝露が多い
夜のうちに地表が冷え、空気中の水分が露になると、翌日は晴れることが多い。
まとめ
身近な自然の様子を観察することで、天気の変化を予測することができます。
飛行機雲の消え方、鳥の飛び方、夕日の色など、ちょっとしたお散歩の中で子どもたちと一緒に観察してみましょう。
自然が教えてくれるサインを見つけて、天気予報を楽しんでみませんか?