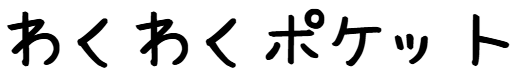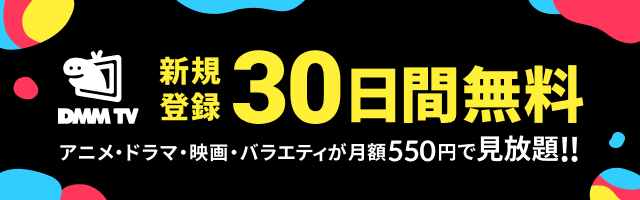日本では、子どもが生まれてからの成長を祝う行事や節目がたくさんあります。
それぞれの節目には、家族や親しい人たちと一緒にお祝いをして、赤ちゃんや子どもが健やかに成長することを願う気持ちが込められています。
最近では、伝統的な祝い方が少しずつ変わってきて、家族や友人ともっと自由に楽しくお祝いする方法も増えています。
この記事では、子どもの命名から長寿のお祝いまで、各節目の意味や最近の傾向を紹介します。
これからのお祝いの参考にしてみてくださいね。
日本の子どもの成長とお祝いの節目
日本には、子どもの成長をお祝いするための大切な節目がたくさんあります。赤ちゃんの誕生を祝うものから、成人式や長寿祝いまで、どれも特別な意味があります。
それぞれのお祝いがどんな意味を持っているのか、どんなふうに行われているのかを見ていきましょう。
お七夜(七日祝い) – 生後7日目
お七夜は、赤ちゃんが生まれて7日目に行う命名の儀式です。
この日、赤ちゃんに名前をつけて、家族や親しい人たちにその名前を披露するのが一般的です。昔から「名付け親」が名前を決めることが多かったのですが、最近ではパパやママが自分たちで名前をつけることがほとんどです。
近年の傾向:
最近では、お七夜の儀式を簡素にしたり、オンラインで家族や親戚と名前を発表するスタイルも増えています。お祝いの形式が少しカジュアルになり、みんなでリラックスして過ごすことができるようになっています。
お宮参り – 生後1ヶ月頃
お宮参りは、赤ちゃんが生まれて1ヶ月ほど経ったころに神社にお参りをして、赤ちゃんの健康と成長を祈る行事です。神社でお祈りをすることで、家族全員で赤ちゃんの未来を祝います。
近年の傾向:
お宮参りも、家族で記念写真を撮ったり、スタジオでの撮影が人気です。最近では、オンラインで参拝することもできる神社もあるので、遠方に住んでいる親戚と一緒にお祝いする方法も増えています。
子どもの節目のお祝い
3歳、5歳、7歳という節目の年齢では、子どもの成長を祝う「七五三」という行事があります。これは、特に女の子と男の子の成長を祝う大切なお祝いです。
七五三 – 3歳、5歳、7歳
七五三は、子どもが3歳、5歳、7歳を迎える時に行うお祝いです。女の子は3歳と7歳、男の子は5歳に神社にお参りし、これからの健やかな成長を祈ります。お祝いの日には、着物を着るのが一般的で、家族で記念撮影をすることが多いです。
近年の傾向:
最近では、七五三の祝い方も少し変わってきています。家族で神社に行くだけでなく、親しい友人と一緒にお祝いしたり、フォトスタジオでの撮影が人気です。また、SNSで写真をシェアすることも多く、晴れ姿をたくさん残すことができます。
成人から長寿祝いまでの大切な節目
成人式や長寿のお祝いは、人生の大きな節目としてとても大事にされています。これらのお祝いは、家族や友人、地域の人たちと一緒に過ごすことが多いです。
成人式 – 20歳
成人式は、20歳になったことを祝う儀式で、正式に大人として社会に出る準備をする日です。20歳を迎えることで、責任を持ち、大人としての自覚を促す意味もあります。成人式では、着物やスーツを着て、式典に参加するのが一般的です。
近年の傾向:
成人式は、最近では地域によって違いがありますが、コロナ禍の影響でオンライン成人式や小規模な集まりも増えました。着物やスーツでのお祝いは変わらず人気ですが、レンタル着物やカジュアルなスタイルでお祝いする人も多くなっています。
還暦 – 60歳

還暦は、60歳を迎える節目の祝いです。この年齢は、「干支」が一周することから、新しいスタートを意味します。赤いちゃんちゃんこを着るのが伝統的なスタイルですが、最近では、もっとカジュアルに楽しむ方が増えています。
近年の傾向:
還暦祝いでは、家族や友人を招いて食事会を開いたり、旅行に出かけることも人気です。赤いちゃんちゃんこを着る代わりに、赤い色を取り入れたファッションで祝うことも増えています。
長寿祝いの節目とその意味
日本では、長寿を迎えることを祝う行事もとても大切にされています。これらの祝いは、家族や友人と一緒に、長い人生を祝う特別な機会です。
70歳:古希(こき)
古希は70歳を迎える年齢で、「古希」という言葉は中国の詩人・杜甫の詩から由来しています。この詩の中で70歳を「人生の大きな節目」と称賛し、古希という言葉が生まれました。
祝いの意味
- 70年という長い人生を生きてきたことを祝う意味合いが込められています。
- 「古希」の「古」や「希」は、古代における70歳の長寿を称えるものとして、特別な意味を持ちます。
77歳:喜寿(きじゅ)
喜寿は77歳を迎える年齢で、こちらも日本の長寿に関わる祝いの一つです。
「喜寿」の「喜」は、漢字が「七十七」の文字を変形した形であることに由来しています。これは、長い人生を喜びとともに祝う意味合いが込められており、家族や周囲からのお祝いの言葉が多くあります。
祝いの意味
77年という長い年月を経て、健康で元気に過ごしていることを祝います。また、歳を重ねることで得られる智慧や経験を尊び、さらに豊かな人生を送ることを願うものです。
80歳:傘寿(さんじゅ)
傘寿は80歳を迎える年齢で、漢字の「傘」の字が「八十」に似ていることから名づけられました。この年齢は、古くから大きな節目として考えられており、家庭や親しい人々との絆を深める時間です。
祝いの意味
80年という年月にわたる人生の歩みを祝うとともに、長寿をさらに願い、敬意を表します。生活の中での深い知恵や思いやりを感謝する機会でもあります。
88歳:米寿(べいじゅ)
米寿は88歳を迎える年齢で、漢字の「米」が「八十八」に見えることからこの名前がつけられました。この年齢は非常に長寿を祝うもので、家族や友人たちによって盛大にお祝いされます。
祝いの意味
88年という長い年月を生き抜き、その豊かな経験に感謝し、今後も元気に過ごすことを願う気持ちが込められています。日本では、米寿を迎えることは、大きな節目とされる特別な出来事です。
90歳:卒寿(そつじゅ)
卒寿は90歳を迎える年齢の祝いで、「卒」という字が「成し遂げる」という意味が込められています。90年という長い年月を生きてこられたことを祝う重要な節目として位置づけられています。
祝いの意味
- 90年を生き抜いたことに対する敬意と感謝の気持ちを込めて、祝いが行われます。卒寿は、その人生の積み重ねを讃える大切な年齢です。
100歳以上の長寿祝い
100歳を超える長寿のお祝いは、さらに特別な意味を持っています。長寿を祝うお祝いは、家族や友人、地域社会と共にその生きざまを讃える大切な行事です。100歳を迎える「百寿」や、それを超える「紀寿」「茶寿」などの祝いも行われています。
百寿 – 100歳
100歳を迎えるお祝いは「百寿」と呼ばれ、非常に重要な節目として広く祝われます。日本では100歳を迎えることが一つの大きな目標とされ、特に家族や地域の人々と一緒に盛大に祝うことが多いです。百寿を迎える方には、自治体からの祝い状や感謝状が送られることが一般的です。
紀寿 – 105歳
紀寿(きじゅ)は、105歳を迎える長寿のお祝いで、古くから日本に伝わるものです。「紀」の字が「長い」という意味を持つことから、105歳を迎えることを祝います。紀寿を迎えることは非常に稀であり、この年齢を祝うことは、地域や家族にとっても大変な名誉です。
茶寿 – 108歳
茶寿(ちゃじゅ)は、108歳を迎えるお祝いで、茶の「茶」の字にちなんでいます。108という数字には「煩悩を取り払う」という意味も込められており、108歳の長寿を祝うことは、家族や地域にとっても非常に特別な意味を持っています。
延寿 – 111歳以上
111歳を迎えると「延寿(えんじゅ)」というお祝いもあります。この年齢を迎えるのは、非常に少なく、どれだけ長生きしたかが特別な意味を持ちます。「延」には延命、命を延ばす意味が込められており、さらに長い年月を生きていることを讃える祝いです。
2025年時点『日本最高齢』
現在、日本の最高齢者は岐阜県土岐市に住む『林おかぎ』さん。2025年1月6日時点で115歳です。
林さんは1909年9月2日に土岐市で生まれ、現在は市内の介護施設で生活されています。施設の職員によれば、食欲は旺盛で、行事にも参加されているとのことです。
以前、兵庫県芦屋市に住む116歳の女性が国内最高齢者とされていましたが、2024年12月に亡くなられたため、現在は林さんがその座を継いでいます。
まとめ
日本の伝統的な節目のお祝いは、家族や親しい人たちと一緒に過ごす大切な時間です。赤ちゃんの誕生から長寿を祝う100歳以上の節目まで、それぞれのお祝いには深い意味が込められています。お七夜やお宮参り、七五三といった子どもの成長を祝う行事、成人式や還暦を迎える時の祝い、そして長寿を祝う米寿や百寿、さらに115歳という素晴らしい年齢に達した方々のお祝いまで、すべてが家族や地域の絆を深める素晴らしい機会です。
最近では、伝統的な儀式に加えて、より自由でカジュアルな方法でお祝いすることが増えてきていますが、どんな形式であれ、心からの感謝と祝福の気持ちを込めて大切な節目を祝うことは変わりません。家族で笑顔を交わし、思い出を作りながら過ごす時間は、何よりも温かく、心に残るものです。
これからも、どの年齢の節目であれ、家族と共にその瞬間を大切にし、健康と幸せを願う気持ちを込めてお祝いしていきたいですね。人生の一つ一つの節目が、これからの生き方にとって意味深いものとなりますように。