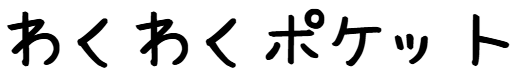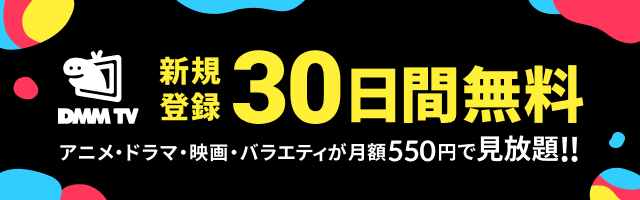「七五三のお祝い、どこから始めればいいか分からない…」
そう感じているあなた、実は多くの家庭が同じ悩みを抱えています。
どんな服装が正解なのか?
参拝のタイミングや神社の選び方は?
兄弟姉妹がいる場合、どうお祝いをまとめればいいのか?
お子様の成長を祝う大切な行事だからこそ、準備に迷ってしまうのは当然です。
この記事では、年齢別の意味や服装の選び方、参拝のタイミング、兄弟がいる場合のベストな方法まで、よく疑問に思い調べられる内容をまとめてみました。
七五三のお祝い年齢
七五三は、子どもの成長を祝う大切な行事で、それぞれの年齢において特別な意味があります。
- 3歳:髪を結うことを始め、成長を祝う。
- 5歳:初めて袴を着て、成人への一歩を踏み出す。
- 7歳:帯を締めることで、女性としての成長を祝う。
それぞれの年齢ごとの意味について、詳しく見てみましょう。
3歳(男女ともに)
- 年齢の意味: 3歳は、子どもが髪の毛を伸ばし始める年齢です。この時期に「髪置き」または「髪結い」が行われます。これが、子どもが成長し、髪の毛を結うことができるようになったという意味合いがあります。古くは髪を伸ばし始めると、子どもが大人に近づいた証として捉えられていました。
- 衣装: 男の子も女の子も、3歳での七五三では、通常、被布(ひふ)という短い着物を着ます。男の子は、袴を着ることもありますが、女の子の方が衣装が華やかで、被布や着物を楽しむことができます。
5歳(男の子)
- 年齢の意味: 5歳は、男の子が初めて「袴」を着る年齢です。これを「袴着(はかまぎ)」と呼びます。この年齢は、男の子が成人に向けて一歩踏み出す意味を込めた儀式です。実際に成人としての生活を意識し始める、成長の重要な時期とされています。
- 衣装: 男の子は、通常、黒や紺色などの袴を着用します。袴の上に紋付きの着物を着ることが多く、伝統的な装いが特徴です。
7歳(女の子)
- 年齢の意味: 7歳は、女の子が初めて「帯」を締める年齢で、これを「帯結い(おびゆい)」と呼びます。7歳は、女の子が成長し、成人に近づくことを象徴する年齢です。この年齢に帯を締めることは、女の子が大人への道を歩み始める意味を込めています。
- 衣装: 女の子は、7歳の七五三で「振袖(ふりそで)」を着ることが一般的です。振袖は、成人式でも見られる華やかな着物で、非常に美しい装いです。帯を締めることが重要なポイントとなり、髪型も豪華に結い上げられることが多いです。

七五三のお祝いの時期
七五三は、基本的には 11月15日 に行われることが伝統的ですが、この日付にこだわらず、その前後の土日や祝日などにお祝いをする家庭も増えてきました。
伝統的な時期
- 11月15日:この日は、元々「吉日」とされ、子どもの成長を祝う日として選ばれました。特に江戸時代から続く慣習です。
- 神社では、この日に神主が祝詞を上げる など、特別な儀式を行うこともあります。
最近の傾向
- 前後の週末や祝日:多くの家庭では、11月15日に限らず、子どもの学校や親の仕事の都合も考慮し、11月の中旬から下旬にかけて祝うことが一般的です。土日や祝日に合わせて参拝することが多くなっています。
- 天候や混雑を避けて:天候や混雑を避けるために、11月の中旬に行う家庭も増えており、特に人気のある神社では混雑を避けるために、早めに参拝することもあります。
神社での参拝タイミング
七五三の参拝は、基本的に 神社 で行います。参拝のタイミングとしては、以下の点を考慮します。
参拝の基本的な流れ
- 参拝日の選定: 七五三の参拝は、前述のように11月15日を基準にしますが、その前後で調整することも多いです。事前に神社の混雑具合を確認するのも一つの方法です。
- 参拝の時間帯: 神社の参拝時間は、通常の日と同じように朝から夕方まで可能ですが、混雑を避けるために午前中早い時間帯 に行くのが理想的です。特に大きな神社や人気のある神社は、午後になると混雑が予想されるため、午前中の参拝が勧められます。
- 参拝方法: 神社では、まず鳥居をくぐり、参道を歩きます。手水舎(ちょうずや)で手を洗い、口をすすいだ後に本殿に向かって参拝します。参拝時には、二礼二拍手一礼 の作法を守ります。神主が祝詞を読み上げ、子どもにお守りや千歳飴(ちとせあめ)を授けてくれることが一般的です。
参拝のタイミングの選び方
- 神社の混雑を避けたい場合:人気の神社では、参拝者が多いため、平日や混雑しにくい時間帯(午前中)を選ぶのが賢明です。特に、子どもを連れていく場合は、混雑を避けることで、よりゆっくりと過ごせます。
- 事前の予約ができる場合も:最近では、七五三のお祝いに特化したプランを提供している神社もあります。こうした神社では、事前に参拝の予約をしたり、専用のプランで神主に祝詞を上げてもらったりすることができます。
七五三の参拝におけるマナー
- 神社に参拝する際は、静かに、敬意を持って行動することが大切です。子どもにも礼儀を教えながら、手を合わせ、神様に感謝の気持ちを伝えましょう。
- 衣装を着た子どもは特に目立ちますので、他の参拝者への配慮も忘れないようにします。
両親の服装はどうする?
七五三の際、親の服装については、子どもを祝う特別な日なので、きちんとした格好が求められますが、あまり堅苦しくなく、シーンに合った服装を選ぶことが大切です。
父親の服装
父親の服装は、七五三の参拝にふさわしいフォーマルな服装が求められますが、過度に堅苦しくなく、シンプルかつ品のあるスタイルが適しています。
1. スーツ(ビジネススーツ)
- 一般的な服装:スーツを着るのが一般的です。黒や濃紺、グレーのスーツが好まれます。
- シャツとネクタイ:白のシャツに、落ち着いた色合いのネクタイを合わせます。ネクタイの色は派手すぎない方が良いでしょう(例:シルバー、ネイビー、深いグリーンなど)。
- 靴:革靴を履き、きちんと磨いておくことが大切です。色は黒か茶色が無難です。
2. 和装
- 正式な和装(紋付き袴)を着ることもありますが、これはかなりフォーマルであり、一般的には結婚式や特別な場面で多く見られる服装です。七五三の場合、父親が和装を選ぶことは少ないですが、伝統を重んじて着る家庭もあります。
3. カジュアルスタイル
- もし、式典がカジュアルな雰囲気で行われる場合、シンプルなジャケットとチノパンなどのカジュアルスーツでも問題ありませんが、あまりにもカジュアルすぎないように注意しましょう。セーターやカジュアルなジャケットでは、ややラフに見える可能性があります。
母親の服装
母親の服装も、七五三の祝いにふさわしいきちんとしたものが望まれます。特に女性の場合、華やかさや優雅さを演出することが求められます。
1. 和装(着物)
- 着物(振袖や訪問着):七五三のとき、母親が着物を着ることもあります。特に女の子の七五三では、母親が着物を着るのが一般的です。振袖や訪問着を選ぶことが多いですが、あまり派手すぎず、シンプルで品のあるものが良いとされています。
- 帯や小物:着物には帯や小物(帯締め、帯揚げなど)も重要です。これらをきちんと合わせて、全体のバランスを考えましょう。
2. フォーマルドレス(ワンピース)
- ワンピースやドレス:最近では、フォーマルなワンピースやドレスを選ぶ母親も増えています。色は落ち着いた色(黒、紺、ベージュ、ダークグリーンなど)が一般的ですが、華やかさを出すために刺繍やレースが施されたものを選ぶこともあります。
- ジャケットやボレロ:ドレスやワンピースに合わせて、ジャケットやボレロを羽織ることもあります。これにより、さらにフォーマル感を出すことができます。
3. スーツ(ビジネススーツ)
- 女性用スーツ:母親がビジネススーツを着ることもあります。落ち着いた色のジャケットとスカート、もしくはパンツスーツを選ぶことが一般的です。カジュアルすぎないよう、フォーマル感を保ちつつ、子どもを祝う日らしい清潔感と品を大切にしましょう。
4. カジュアルなスタイル
- 七五三のお祝いがカジュアルな雰囲気で行われる場合、シンプルなブラウスとスカート、ワンピースなどを選ぶこともあります。ただし、あまりにもカジュアルすぎる服装(ジーンズやカジュアルシャツ)は避ける方が無難です。
注意すべきポイント
- 色選び:七五三の参拝時には、あまり派手な色や露出の多い服装は避け、落ち着いた色合いの服を選ぶと良いでしょう。特に神社などでの参拝時は、清楚で品のある服装が望まれます。
- 季節感:11月は秋から冬にかけてなので、温かみのある素材やコートなどを合わせることも考慮しましょう。
- 子どもに合わせる:母親や父親の服装は、子どもが着る伝統的な衣装と調和させると、より美しい印象になります。例えば、女の子が振袖を着るなら、母親も着物を着るといった形です。
兄弟(姉妹)がいる場合のお祝い
兄弟がいる場合の七五三の祝いについても考慮するポイントがあります。特に、複数の子どもが七五三を迎える場合、衣装や参拝のタイミングをどう調整するかが重要です。兄弟姉妹がいる場合の七五三に関するポイント説明します。
1. 兄弟姉妹が同時に七五三を迎える場合
もし、兄弟姉妹が同じ年に七五三を迎える場合(例えば、5歳と7歳の男の子と女の子が同時に七五三を迎える)、お祝いを同時に行うことが一般的です。これにより、両方の子どもが一緒に祝われるため、家族全体での思い出深いイベントとなります。
衣装の調整
- 男の子は、5歳の七五三で袴を着るのが一般的です。兄弟がいる場合も、それぞれが年齢に合わせた服装を選びます。
- 女の子は、3歳で「被布」、7歳で「振袖」を着ることが一般的です。同時に兄妹の七五三を祝う場合でも、個々の年齢に応じた衣装を着せます。
- 兄弟姉妹で衣装のカラーやデザインが調和するようにすると、家族全体の統一感が出て素敵です。
参拝のタイミング
- 兄弟姉妹が同時に七五三を迎える場合、参拝は一緒に行うことが多いです。参拝の順番としては、まず子どもたちを神社に連れて行き、みんなで一緒に参拝します。その後、個別に写真撮影を行うこともあります。
- もし参拝日が忙しくなりそうな場合(例えば、人気の神社などで混雑している場合)、時間帯や日にちを分けて参拝することも可能です。特に大きな神社では、1回の参拝で複数の子どもを祝うことも多いため、時間帯を選んで行動するのが賢明です。
2. 兄弟姉妹が異なる年齢で七五三を迎える場合
兄弟姉妹が異なる年齢で七五三を迎える場合(例えば、3歳と7歳の子どもがそれぞれ七五三を迎える場合)でも、お祝いを一緒に行うことができます。
衣装の選び方
- 3歳の子どもは、通常「被布」や着物を着ることが一般的です。男の子は袴、女の子は被布を選びます。
- 7歳の子どもは、女の子は「振袖」を着ることが多く、男の子は「袴」を着ます。
それぞれの子どもが異なる年齢のため、衣装が異なることは当然ですが、家族全体での統一感を意識して、衣装の色やデザインを少し調整すると、より一層お祝いの雰囲気が盛り上がります。
参拝のタイミング
- 兄弟姉妹が異なる年齢で七五三を迎える場合でも、基本的には同じ日に一緒に参拝することが一般的です。参拝の際は、年齢ごとに少しだけ順番を調整し、親も一緒に参拝します。
- 同時に祝うことで、家族全員が一つのイベントとして一体感を持つことができます。参拝後にそれぞれの子どもの写真を撮ることもできます。
- 参拝や写真撮影の際には、年齢が上の子どもから先に参拝を行い、次に下の子どもが続く形で進めることが一般的です。
4. 兄弟姉妹の七五三を分けて行う場合
もし兄弟姉妹がそれぞれ異なる年に七五三を迎える場合や、都合で一緒にお祝いできない場合でも、個別に七五三を祝うこともできます。その場合、以下のように分けて行います:
- 年ごとに祝いの日を分ける:例えば、1年おきに七五三を祝う、もしくは他の家族行事と重ならない日に個別に祝います。
- 写真撮影を別日で行う:撮影は同じ日に行わず、七五三の参拝と撮影を別日で行う家庭もあります。
まとめ
子どもの成長を祝う行事だからこそ、どうしたら素敵な思い出を創れるのか悩む人は多いと思います。
実際に三日月も3歳と1歳の息子達がいて、七五三はどうすべきか悶々としていますし・・・。
我が家は長男5歳と次男3歳のタイミング、次男5歳と長男7歳のタイミングで参拝と写真を撮ろうかなと考え中です。両親と夫婦、家族で話し合って、自分たちの家に合ったタイミングでお祝いできるといいですね。
どんなタイミング・形にせよ、家族の思い出に残る素敵な日になるように、心を込めてお祝いすることが大切だと思う三日月でした。
皆様、素敵な七五三をお祝いできますように!!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。